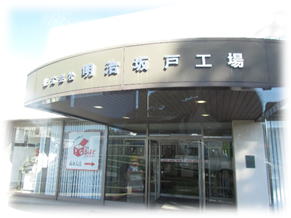�݂���Γ��L
�U���Q�U���i���j�u�T�N�����b��v
�����͂T�N���Ɍ������u���b��v���s���܂����B���b��́A�}���{�����e�B�A���A���ꂼ��̊w�N�ɍ��킹�āA�{�́u�ǂݕ������v��u���ŋ��v�A�u�p�l���V�A�^�[�v����ʂ��āA�{�̖��͂��Љ����̂ł��B�����G�߂ɓ���A�����ł��������C�����ɂȂ��ė~�����Ƃ����v�������߂āA�}���{�����e�B�A���Љ�Ă��ꂽ�{�́A�|���{�𒆐S�ɏЉ�Ă��������܂����B�܂��A�X�ɖ{�̐��E�ɓ��荞�߂�悤�������Â����āA���͋C�Â���ɂ��w�߂Ă��������܂����B�q�������́A�}���{�����e�B�A����̓ǂݕ������₨�b�̓��e������A�{�̐��E�ɓ����Ă���悤�ł������A���������w�N�ł��B�u�|���b����������A�ŏ��̓\���\���A�h�L�h�L��������ǁA�ŏI�I�ɂ͖ʔ��������B�v�ƌ����Ă��銴�z��������܂����B�S�������������Ă��܂��ˁB�}���{�����e�B�A�̊F�l�A�u���b��v��ʂ��āA�{�̖��͂��q�������ɂ��`�����������A���肪�Ƃ��������܂����B

�U���P�X���i�j�@�S�Z�S�������i�Ɗԋx�݁j
�U�����{�ɂ�������炸�A�����Ԃ�Ə����G�߂ɂȂ��Ă��܂������A�q�������͍��������C�ɉ߂����Ă��܂����B�����̂P�E�Q���Ԗڂ́A�P�E�Q�N���̑̈�̊w�K�u�V�̗̓e�X�g�v���s���A���̂���`�����U�N��������Ă���܂����B�U�N���̎�����T�|�[�g���A�P�E�Q�N�����S�͂��o���낤�Ɓu�����̑O���v�u���������сv�u�Q�O���V���g�������v�u��̋N�����v�u���������сv�Ɏ��g��ł��܂����B���̌�A�Ɗԋx�݂ɂ͉^���ψ���������Ă��ꂽ�u�S�Z�S�������v���s���܂����B�u�S�Z�S�������v�́A�O���́u�X�S�v���s���A�㔼�́u�ς��S�v���s���܂����B�S�������̋S���́A�u�X�S�v�ł͂U�N���Ɖ^���ψ��A�u�ς��S�v�͉^���ψ����ŏ��͍s���Ă��܂����B�S�ɂȂ��������́A�݂�Ȕ��F�X�q�ɕς���Ƃ������[��������āA�y�������Ɋ������Ă��܂����B�^���ψ���̊F����A�y�����������肪�Ƃ��������܂����B���������������A���C�ǂ��^�����܂����̂ŁA���q�l�����Ă��邱�ƂƎv���܂��B�\���Ȑ������Ƃ�悤���肢���܂��B
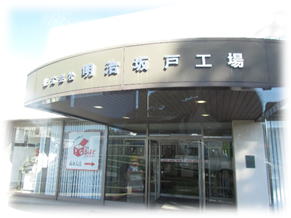
�U���P�W���i���j�@�Ǐ��^�C���i�ǂݕ������j
�����́A�}���{�����e�B�A����ɂ��u�ǂݕ������v������܂����B�q�������́A�G�{����D���Ȃ悤�ŁA�}���{�����e�B�A���Љ���G�{��H������悤�Ɍ��Ă��܂����B�@�{�Z�̓ǂݕ������́A���̓Ǐ��^�C���̎��ԂɌ��P��A�}���{�����e�B�A���S�w���ŁA�I�肷����̖{���Љ�Ă������̂ł��B�ǂ̂悤�ȊG�{���Љ��Ă����̂��A���ƒ�ł��b��ɂ��Ă݂Ă��������B

�U���P�V���i�j�u�R�N�����R�[�_�[�u�K��v
�����͂R�N���́u���R�[�_�[�u�K��v������܂����B�u�t�Ƃ��āA�������R�[�_�[����̒���
�F�� �搶�����������A���R�[�_�[�̐��������͂��߁A���R�[�_�[�̖��͂��Љ�Ă��������܂����B���R�[�_�[�̐������ł́A1�����u�g�D�A�g�D�c�c�v�Ɛ�Ő�u�^���M���O�v�Ƃ����u���ꂢ�ɕ�������v�u�������悭��������v���t���@�������܂����B�܂��A�����搶�́u���R�[�_�[�łǂ�ȋȂ������邩�ȁH�v�Ǝq�������ɖ₢��������A�\�v���j�[�m�A�\�v���m�A�A���g�A�e�i�[�A�o�X�Ȃǃ��R�[�_�[�̎�ނɍ��킹�āA�l�X�ȋȂ��I���Ă��������܂����B��I���Ă��ꂽ�Ȃ́A�ƂȂ�̃g�g���u����ہv�A�m�g�j����e���r�u�s�^�S���X�C�b�`�v�A�u�S�ł̐n�v�̎��́u���v�u�J�m��Ձv�ACreepy Nuts�uBling�]Bang�]Bang�]Born�v�A�Ȃǂł��B�q�������̓���݂̂���Ȃ����������I���Ă�������A�q�������͊y�������Ɍ������݁A�g�̂�h�炵�ă��Y�����Ƃ��Ă��܂����B���̌�A�����搶�ƈꏏ�ɓ��w�E���́u�����[����̗r�v�����t���܂����B���R�[�_�[�̊y������������ƂƂ��ɁA���R�[�_�[�̉\�����L���Ă��������������F���搶�A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�U���P�S���i�y�j���]�n�揬���w�Z�e�r���Z���
��T�P�S���i�y�j�́A�R�����w�Z�ło�s�`��Ấu���]�n�揬���w�Z�e�r���Z���v������܂����B���Z���̓��e�́u�\�t�g�o���[�{�[���v�ł��B�܂��A�Q���Z�͖{�Z�A�R�����A�R�����A�쏬�A���Ԗ쏬�A���Ԗ쒆�̂U�Z�ł��B�e�Z�̗L�u�̕ی�҂̕��X�Ƌ��E�����ꏏ�̃`�[���Ƃ��āA���̂T�Z�Ƒ��������ŏ��s�������Ȃ���A�e�r��[�߂銈���ł��B�{�Z�ł��A�\�t�g�o���[�{�[���Ƃ����X�|�[�c�̓��������ăg�X���Ȃ��ő���R�[�g�Ƀ{�[�������邱�Ƃ�A�g�X����̃A�^�b�N�Ƃ����A�W�v���[�����邱�ƁA�~�X���J�o�[����������A��܂��������肷�邱�ƂŃ`�[���ӎ������܂�A�����E�ی�҂̘g���Ă݂�Ȃ̐e�r���[�܂���g�݂ł������悤�Ɏv���܂��B�@�{�Z�̎Q���������������X�̂��s�͂ɂ��A�u���D���v���l���ł��܂����B���Q�������������ی�҂̊F�l�A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B���N�x�́A�{�Z�Łu���]�n�揬���w�Z�e�r���Z���v���Â��\��ł��B�ی�҂̊F�l�A���̍ۂ́A�ӂ���Ă��Q�����������B

�U���P�R���i���j�@��P���ʈ��S����
�{���̂Q�`�S���Ԗڂ́u��ʈ��S�����v��̈�قɂĎ��{���܂����B���B�i�K�ɉ����ē`�B������e���قȂ邽�߁A�Q���Ԗڂ͂P�E�Q�N���A�R���Ԗڂ͂R�E�S�N���A�S���Ԗڂ͂T�E�U�N���ƁA�w�N�u���b�N���ƂɎ��g�݂܂����B���Z�������A��ʎw��������S���ɂ����͂��������A�u���s�E���f���K�v�u���]�Ԃ̐����������w���i�w���������j�v�u�ʊw�ǐ��o���A���U��w���v�ȂǂɎ��g�݂܂����B���ꂼ�ꂪ�A�K�x�ȋْ����̒��A��̋������≡�f�����ł̒��ӓ_�A�ǂ݂̂�Ȃւ̌��t�����ȂǁA�O�����ɗ��K�����Ă��܂����B�{���̓��H�≡�f�����ł͂Ȃ����ł̗��K�������̂ŁA�p���������l�q�̎����������悤�Ɋ����܂����A�I���܂������ɂ��Ď�������邱�ƁB���E�̊m�F���s�����ƂȂnj��t�����������Ȃ���A���m�F���Ȃ�����g�߂Ă��܂����B�{�Z�ߕӂ́A��ʗʂ̑������H�ɉ����A�ׂ��ԓ�����������܂��B�{���A���g�u��ʈ��S�����v�A���̐U��Ԃ�A�܂��A�ʊw�lj�c���͂��߂Ƃ���w������ʂ��A���ꏬ�w�Z�����̌�ʎ����g�O�h��ڎw���A�w���E�x�����Ă܂���܂��B���ƒ�ł����q�l�ƁA��ʃ��[��������ĉ߂������Ƃɂ��Ęb��ɂ��Ă݂Ă��������B

�U���P�Q���i�j�S�N���Љ�Ȍ��w
�����A�S�N���͎Љ�Ȍ��w�ɍs���܂����B�s��͋��R�s���ɂ���u��R���Z���^�[�v�Ɓu���������فi�v���l�^���E���j�v�ł��B�u��R���Z���^�[�v�ł́A�ƒ납��o���ꂽ�S�~���ǂ̂悤�ɉ^��A��������A���ɐ��܂�ς��̂������ۂɌ��Ċw��ł��܂����B�S�~�����Z���^�[�̃S�~���^�ԃN���[���𑀍삵�Ă���l���K���X�z���Ɍ�����A�S�~���W�Ԃɐύڂ����S�~�̏d�����v��v����Ɏq��������������肵�āA���߂Ēm�������Ƃւ̑f���Ȕ����ɁA�S�N���̑̌���ʂ��Ă̊w�т������܂����B�u���������فv�ł́A�v���l�^���E���Ő��̓�������̐����A�����₻�̗R���ɂ��Ċw�т܂����B������������Ɓu���͂���Ȃɐ�������̂��I�v�Ɛ��̑������Y�킳�Ɏq�������͊������Ă��܂����B��N�̌��w�Łu�Ă̑�O�p�̈�ʼnΐ��̃��C�o���Ƃ��Ă��u�A���^���X�v�Ƃ����ꓙ���̊o�����Ƃ��āA�u���N�ł��H�v�u�A���^���X�v�Ƃ����E���̃��Y�~�J���Ȍ��t���w�сA�݂�Ȃ��o���Ă������Ƃ�E�����ق߂Ă���Ă��܂����B�܂��A�����b�ɂȂ������X�A�o�X�̉^�]�肳��ɂ�����̈��A�ȂǁA�w�K�ȊO�ɂ��Ă������̎q����������Ǝ��g�߂Ă��܂����B

�U���P�P���i���j�@�X�}�C���[�u�c����V�сv
����A�C�ے��͊֓��b�M�Ɩk���n�����u�~�J���肵���Ƃ݂���v�Ɣ��\���܂����B�������A���ꏬ�݂̂�Ȃ́A���̂悤�ȓV�C�ɂ��������A�{���̓X�}�C���[�^�C���u�c���芈���v���������X�^�[�g���܂����B�u�c���芈���v�́A�@�ٔN��W�c�̊�����ʂ��āA�]�܂����l�ԊW��Љ����Ă邱���A���B�i�K�ɉ��������含�E���H�͂���Ă邱�Ƃ̂Q�_��ڕW�Ƃ��Ă��܂��B�{�����A�U�N���̂��o���Z����𒆐S�ɁA�e�����Ŋ����Ɏ��g�݂܂����B�O�̉J���������������炢�A�e�O���[�v�̊����ɐ���オ�肪�����܂����B�u�n���J�`���Ƃ��v�u�֎q���Q�[���v�u�����Q�[���v�u�t���[�c�o�X�P�b�g�v�ȂǁA�݂�ȂŊy���߂�V�сE���[���̍H�v�������܂����B�܂��A����������������w�N�̎����ɑ��āA���w�N�̎����炪�܂��S������Ă��Ȃ��l�Ƃ̌����Ă�����A���w�N����������ȊO�̎�����ǂ�������X�s�[�h�ɔz��������ƁA�w�݂�ȂŊy���ށA�݂�ȂŌ��シ�邽�߂Ɂx�Ƃ����p�����e�O���[�v�Ō����A�����ւS�������܂����B���̂悢���͋C���A�N���X�ł̎��Ƃ�s���A�o���Z�A�x�ݎ��Ԃ̊ւ��ɂƁA�X�ɑ傫���L�����Ă������Ƃ����҂��Ă��܂��B

�U���X���i���j�@�����Ȓ��T��
�����A�Q�N���́u�ǂ�Ȃ��̂��w�Z�̋߂��ɂ͂��邩�ȁH�I�v���߂��ĂɁA�����Ȃ̊w�K�̈�ŁA�w�Z�̎���̒��T���ɍs���܂����B�����́A�w�Z���狷�R�X�C�~���O�N���u�A�������A��ł��ΐr��̑O��ʂ�A�t�@�~���[�}�[�g�܂Ō������܂����B���f����������Ă���ƁA�q�������́A��������āu�n��܂��I�v�Ƒ傫�Ȑ����o���ƂƂ��ɁA�ʍs�l�̐l�Ƃ��u����ɂ��́I�v�ƌ��C�悭���A���ł��A�C�����̗ǂ��ԓx�ł����B�܂��A���j�w�K�ł����b�ɂȂ������R�X�C�~���O�N���u�̃X�^�b�t�̕��ɂ������ƁA�q�������͏Ί�Ŏ��U��A�X�^�b�t�̕������ꂵ�����ɂ��Ă����̂���ۓI�ł����B�S�C�̋{��搶���w�Z���牽�����炢�ŕ����Ă�����̂����ӎ������Ȃ��璬�T�������Ă���ƁA�u�������炢�œ����ł������I�v�ȂǁA���Ԃ̊��o���g�ɂ��Ă��Ă���悤�ł����B���T�������Ă���ƁA�u���̂��X�A����������������B�v�u���̂��X�A��������̂��ꂳ�����Ă���Ƃ��낾��B�v�Ȃǂ��낢��ȏ����q�������������Ă���܂����B�q�������́A�悭���������Ă���ȁ`�Ɗ��S���܂����B�Q�w���́A���ꏬ�w�Z���ӂ̂��X�ɃC���^�r���[�����钬�T�����v�悵�Ă����܂��B�Q�N���̕ی�҂̊F�l�Ɍ����āA�{�����e�B�A���W���܂��̂ŁA�q�������̈��S�������ɂ����͂��������B

�U���U���i���j�~�j�o�X���
�����́A�R�����w�Z�̉��Ń~�j�o�X���s���܂����B���̎��ԂɁA����́u�~�j�o�X�I����܂���v�ւ̊��ӂ̂��莆���U�N������������I�Ɋe�w�N�̎q�������ɓn���Ă���A���̓��e��m�����ݍZ���͂ƂĂ����ꂵ�����ł����B�@�U�N�������́A�u�s���Ă��܂��I�I�I�v�ƋC�����̓����������o���A�R�����������܂����B�R�����֓������A�R�����w�Z�̎q�������̐l���������̂ɂ��ւ�炸�A��炪�U�N�����������́A�ŏ�����f���炵���ԓx�ł̂���ł���܂����B���������悭����A�悭�p�X���A�����|�������A��������Ɖ�������p�������܂����B�����ƊςĂ������Ǝv���銈��Ԃ�ł����B���J�Ƀ{�[�����^�сA���������ăV���[�g�����߂Ă���p����A�ςݏd�˂Ă������K�͉R�����Ȃ����Ƃ��������Ă����悤�Ɏv���܂��B�܂��A���Ԃ��܂��A�~�X�����Ă��u�h���}�C�I�v�Ƃ݂�ȂŌ����镵�͋C���������܂����B�l�v���[�ɑ��炸�A�f���炵���`�[�����[�N�������A�w�N�Ő���Ă���p����A���ꂩ��̂U�N���̊��X�Ɋy���݂ɂȂ�܂����B���I���A�U�N���́A�����Č��ꏬ�w�Z�ɋA���Ă��܂����B6�N���̊F����A�~�j�o�X���A�{���ɂ����l�ł����B�����́A�������x��ł��������B�����āA���ꂩ����������̂���{�Ƃ��Ċ��Ă��������I�I�I�ی�҂̊F�l�A�{���́A�����������A���肪�Ƃ��������܂����B


�U�N�������H�̎��Ԃ̊ԋ߂ɋA���Ă����ݍZ���ɂ��`���A�ݍZ�����ɂ�邨�}���̉ԓ�������A����Ŋ��}���Ă���p����ۓI�ł����B6�N�����u���肪�Ƃ��I�v�ƌ����Ă���p����A�������C�����ɂȂ�܂����B�ݍZ���̊F������A���肪�Ƃ��������܂����B
�U���T���i�j�@���Ȍ��f
�����́A���Ȍ��f������܂����B���Ȍ��f�́A���C�⒎���⎕���a�̊m�F�̂ق��A���ݍ��킹��{�̊߂Ɉُ킪�Ȃ������̌��f��������̂ł��B�w�Z���Ȉ�̏���
���W�搶�́A�q��������l��l�J�Ɋm�F���Ă��������܂����B���̒��J�Ȍ��f�����Ă���Ă���p�ɉ�����悤�ɁA�q�������͐Â��ɕ��сA�����̏��Ԃ��I��������ɁA��������Ƃ���������Ă��܂����B�����搶����́A�u���w���̍����玕��҂Œ����\�h�����Ă����l�́A��l�ɂȂ��Ă���v�Ȏ����ێ����邱�Ƃ��ł��Ă���Ƃ������Ƃ��ŋ߂̒����ŗ�����Ă���̂ŁA�ی�҂̊F������Z�����Ƃ͎v���܂����A���q�l�Ɏ���҂Œ���I�i�R�`�S�����Ɉ�x�j�Ƀ����e�i���X���Ă��炢�����ł��B�v�Ƃ̂��b�����������܂����B���́A���N���ێ������ŁA�ƂĂ���Ȗ������ʂ����Ă��܂��̂ŁA���ЁA�����̎��������ɂ���ƂƂ��Ɏ���҂́u�����e�i���X�v�Ƃ��ƒ�ł́u�d�グ�����v�ɂ������͂��������B

�U���S���i���j�@�w�Z�h�{�m�ɂ��H��w��
�����́A�w�Z���H�Z���^�[�̊w�Z�h�{�m�̕��X�����Z���A���H�̎��ԂɂQ�E�R�N���Ɍ����āu�H��w���v�����Ă���܂����B�Q�N���ɂ́A�u���������܂��B�v�u���y���l�ł����B�v�̈Ӗ������b�����Ă��������܂����B�u���������܂��B�v�́A�������������Ă���H�ו��ɑ��Ċ��ӂ̋C�����������ĐH�ׂ邱�Ƃ��Ӗ����Ă��邻���ł��B�܂��A�u���y���l�ł����B�v�́A�X�[�p�[�}�[�P�b�g�̂Ȃ�����́A�y�������ĐH�ނ̏��������Ă����l�ւ̊��ӂ�`����Ӗ����琶�܂ꂽ�Ƃ������Ƃ������Ă��������܂����B�R�N���́A���N�ȑ̂����ɂ́A��D���Ȃ��̂�����H�ׂ�̂ł͂Ȃ��A���ȐH�ו��ɂ����킵�A�o�����X�ǂ��A�����H�ׂ邱�Ƃ���ł��邱�Ƃ����b�����Ă��������܂����B�܂��A��l�ɂȂ��Ă��o�����X�悭�H�ׂ�K�v���ɂ��Ă����J�ɓ`���Ă��������܂����B�l�Ԃ̑̂̍זE�͑�l�ɂȂ��Ă�������܂�ς��܂��B�Q�Ă���Ԃ��S�������A�̉���ۂ��߂ɂ������l�X�Ȃ��̂�H�ׂ邱�Ƃ���ł��邱�Ƃ����b���Ă��������܂����B�q�������́A�h�{�m�̕��X�̂��b���Ȃ���A�Â��ɋ��H��H�ׂĂ��܂����B
�w�Z���H�Z���^�[�ł́A�H�ނ��������A�������E�����������łȂ��A�r�j�[����܁E�}�X�N�ɂ��Ă��A�O�ꂵ�ĉq���ʂɔz�����ċ��H������Ă��܂��B�܂��A�h�{�̃o�����X�����łȂ��A�{�̐H�ו����������Ďq���������H�ɋ����������ĐH�ׂ���悤�H�v�������j���[���l���č���Ă��܂��B���H���D�������Ȃ��H�ׂ���悤�A���ƒ�ł������|�������肢���܂��B

�U���S���i���j��������u�~�j�o�X�I����܂���v
�����̎����W��́A�U���U���i���j�R�����w�Z�ōs����~�j�o�X�P�b�g�{�[�����Ɍ����āA�T�N�������S�ƂȂ�A�S�Z�����ƂƂ��ɑI��i�U�N���j���܂�����s���܂����B�U�N���͑��Ɍ����āA�̈�̎��Ԃ�x�ݎ��Ԃɂ����K���d�˂Ă��܂����B�I��̒��ɂ́A��������ی���Z��Ŏ���I�ɗ��K�ɗ��ł����قǂł��B�I��̊撣���Ă���p�͎��������E���ɂ���������`����Ă��܂����B��܂���ł��^���ȑԓx�ŗՂ݁A�ӋC���݂ƑS�Z�����Ɋ��ӂ̌��t��`���Ă���p�͂ƂĂ��i�D�ǂ������ł��B�܂��A5�N���̉����c�𒆐S�Ƃ����S�Z�����̐���t�̃G�[���A�����c�̊F����̑傫�Ȑ����A����グ�Ă��܂����B�I�肽���ɂ�������Ɠ͂������ƂƎv���܂��B�I��̊F����A�o�X�P�b�g�{�[���́A���_�������X�|�[�c�ł��B���s�̂����̂ł͂���܂����A���s�����ŏI���ɂ���̂ł͂Ȃ��A���Ԃ�M���A���͂��������ƁB�����̗͂��o���邱�ƁB�����āA�N���̊撣���F�߁A�S���甏��𑗂�邱�ƁB�����̑�����w��ł��Ăق����Ǝv���܂��B�����āA�����āA���ꏬ�w�Z�ɋA���Ă��Ă��������ˁB

�U���R���i�j�u�w�Z�^�c���c��v�Ɓu�u�b�W��v
�����́A�w�Z�^�c���c�����܂����B���c���̊F�l��PTA���c��Ƃ́A���K�͍Z�ł��邪�̂ɐ�����{�Z�̂R�̉ۑ�u�s�o�Z�����ւ̊w�K�x���̐��݂̍���v�u���������ɔ������|���̉��P�v�u�o���Z���܂߂����S�E���S�Ȋ��̐����v�ɂ��Ęb�������܂����B�ψ��̊F�l�������ɂł��邱�Ƃ͉����A�ǂ�ȂƂ���ƘA�g��}��悢�̂��A�������Ƃ��ďn�c���s���Ă��������܂����B�n��̊F�l�ɁA���̂悤�ȊF�l�����Ă������邱�Ƃɖ{���Ɋ��ӂ�\���グ�����Ǝv���܂��B����A�{�����e�B�A���̕�W���s���A�F�l���ɂ������͂������������Ƃ��o�Ă��邩�Ǝv���܂��B���̎��́A���ЁA���͂����݂����������B�܂��A�����x�݂́u�u�b�W��v������܂����B�Z���搶����́u�n�b�s�[�t�F�X�e�B�o���v�̗l�q��傫���X�N���[���ɉf���o���A�n�b�s�[�t�F�X�e�B�o�����f�G�Ȏv���o�ɂł������R�́A�݂�ȂŒ��ǂ��y���ނƂ������ʂ̖ڕW����������ɁA��������Ɩ���邱�Ƃ��ł�������ł��B�v�Ƃ������b�ł����B�����āA�u�U���͉J�������A�w�Z���ł��L���⋳���ł͗��������ĉ߂������Ƃɉ����A�Ԃɏ���Ă���l�����E�������Ȃ�܂��̂ŁA�F�������ʈ��S�ɋC�����Ă��������B�v�Ƃ������b�����܂����B�����̐����ڕW�́u���������Đ��������悤�v�ł��B�����搶����́A�L���𑖂�Ȃ��A�K�i���W�����v����Ȃǂ̍s�ׂ���Ȃ��̂ŁA�����������Ƃ��Ȃ��悤��������ĉ߂����Ă����܂��傤�Ƃ������b������܂����B���ꏬ�w�Z�݂̂�ȂŁA���S�E���S�Ȋw�Z�ɂ��Ă����܂��傤�B

�T���Q�X���i�j�U�N���~�j�o�X���K
�����U���߂�������ł��傤���B�ŋ߁A�Z�납�猳�C�Ȑ����������Ă��܂��B���T�U���U���i���j�ɎR�����w�Z�ōs����~�j�o�X���Ɍ����āA�����̎q���������W�܂�A����I�Ƀ~�j�o�X�̗��K�ɗ��ł��܂��B�܂��A���ی���U�N���͎���I�ɗ��K�����Ă���A���Ɍ����āu���������̗͂ŏo�������̂��Ƃ͂�낤�B�v�Ƃ����U�N���̋C�T���A�ƂĂ��������܂��B�U�N���́A���̎��Ԃ����}���\�����S������I������A�̈�قŗ��K���A�Ɗԋx�݂����x�݂��~�j�o�X���K�ɗ��ł��܂��B�������Ė����ɂȂ��āA�݂�ȂŎ��g�����Ƃ��邱�Ƃ��A���̎q�����̍��Y�ɂȂ���̂Ǝv���܂��B���ꏬ�݂̂�ȂŁA�U�N�����������Ă����܂��傤!

�T���Q�V���i�j���ʁu�d�M�v�̊w�K�ɂ���
���ꏬ�w�Z�ł́A���ʁu�d�M�v�̊w�K���n�܂�܂����B�����́A�Z���搶�����w�N�̎��ƂŃA�h�o�C�X�����Ă��������܂����B�Z���搶����́A�T�N���ɂ́u�s�̒��S�v�u�����͑傫�߂ɁA�Ђ炪�Ȃ͏����߂ɏ������Ɓv�u�Ȃ���v�����ӎ����ď������Ƃ��A���ۂɏ����Č����Ă���܂����B�܂��A�U�N���ɂ��Ă͗\�ߏh��ŏ����Ă����q�������̍d�M�̍�i����A�݂�Ȃ̎Q�l�ɂ��ĉӏ����g��@�œd�q���ɉf���A��̓I�ɒ��ڂ��镔���������Ȃ���A�����������Ă���|�C���g��`���܂����B�u�Ȃ�قǁI�v�Ƃ������t���������邭�炢�A�q���������[�����Ă���l�q�ł����B�T�N���A�U�N���Ƃ��Z���搶�̑f���炵���^�M�ɓB�t���ɂȂ邩�̂悤�Ɍ�����A���ۂɏ��������̎��́A����ł悤�ȐÂ����̒��ň���撚�J�ɏ����Ă��܂����B�@�Z���d�M�W�͂U���Q�S���i�j�Q�T���i���j�Q�V���i���j�ł��B���ƎQ�ρE���k��̂�����Ɏ��{�������܂��̂ŁA���q�l�̗͍���A���ЁA�����ɂ����Z���������B

�T���Q�U���i���j�u�V�̗̓e�X�g����E�ی����C��v
�����͎q�����������Z������A�{�Z�̋��E���Ɍ����āu�V�̗̓e�X�g������@���C��v���s���܂����B�̈��C�̍]���搶�𒆐S�ɐV�̗̓e�X�g�̑�����@���m�F���邾���łȂ��A�q�������ւ̎w�����@��w�������ł̐S���E�|�C���g���m�F���܂����B���Ɉӎ����Ă������Ƃ́A�w�͂���p����^���Ɏ��g��ł���ԓx�Ƃ��̉ߒ���J�ߔF�߂Ă������ƂŁA���^���D���Ȏq���������琬���Ă������Ƃł��B����ɂ��A���ʓI�ɍ�N�x�ȏ�Ɏq�������̗̑͂̐L�т�����ꂽ�炢���Ȃƍl���Ă��܂��B�Ȃ��A�{�Z�̎q�������́A�����̎�ڂ���ʌ��̕��ϒl�Ɠ��������������Ă��܂����A�u�����̑O���i�_��j�Ƃ������Ƒсi�����́j�v���A�S�w�N�Ƃ��ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B���ǁE�̈�J�[�h�ɂ��_�����܂����悤�ɁA�����C�オ��̑̂����܂������ɐe�q�ł����{���Ă݂Ă��������B�܂��A�{���̓G�s�y�����p�̌��C����{�싳�@�̒��E�搶�𒆐S�Ɏ��{���܂����B�H���A�����M�[�ɂ���̈����Ȃ��������ɂ��ẴG�s�y���̎g�p���@����A���E���̘A�g�A�Ώ��̎d���ȂǁA���E���ŋ��ʗ�����}��܂����B���̂��N���Ȃ����Ƃ���ԗǂ��̂ł����A�������̎��ɔ����āA���S�Ȋw�Z���ɋ��E���ꓯ�w�߂Ă܂���܂��B

�T���Q�U���i���j�P�E�Q�N�w�Z�T��
�����́A�Q�N�����P�N���Ɋw�Z�{�݂�������u�w�Z�T���v���R�E�S���Ԗڂɍs���܂����B��T�̋��j���́u�Ȃ��悵�W��v�ōX�ɒ��ǂ��ɂȂ����P�E�Q�N�����ꏏ�ɍZ�������Ƃ������ƂŁA�P�N���͂ƂĂ����ꂵ�����ȗl�q�ł����B�P�E�Q�N���͊e�ǂɕ�����āA�R�N���ȏ�̊w���₩���̂��w���̗l�q�����ĉ������A�E������������A���̑��ɂ����Ȏ��≹�y���Ȃǂ̓��ʋ��������ĉ�����肵�܂����B�E�����ɓ����Ă����ǂ̎q�������̗l�q�����Ă݂�ƁA�܂��A����̃h�A����R���R���ƃh�A���m�b�N���A�u���炵�܂��B�w�Z�T���ŗ��܂����B�����Ă���낵���ł����H�v�ƂQ�N�������̗��h�Ȑ����������Ă��܂����B�u�ǂ����I�v�Ɠ`����ƁA�Q�N�����P�N���Ɂu�����́A�搶���W�܂邨��������B�v�ƂP�N���ɋ����Ă���l�q�������܂����B�Q�N���̎����̒��ɂ́A�P�N���Ɂu�ڂ��̐����́A�킩�����H�v�Ɗm�F���Ă���p�������A�P�N���ɂ������苳���悤�Ƃ����g�����������Ă���p�������܂����B�P�N���̊F����A�F��������N�x�́A�V�P�N���Ɋw�Z���ē��ł���悤�A�w�Z�̎{�݂��o���Ă��������ˁB�����āA���̂Q�N���̂悤�ɗ��h�ɐ����ł���l�ɂȂ��Ă��������B�Q�N���̊F����A���肪�Ƃ��������܂����B
�T���Q�R���i���j�u1�N�����b��v
�����͂P�N���Ɍ������u���b��v���s���܂����B���b��́A�}���{�����e�B�A���A���ꂼ��̊w�N�ɍ��킹�āA�{�́u�ǂݕ������v��u���ŋ��v�A�u�p�l���V�A�^�[�v����ʂ��āA�{�̖��͂��Љ����̂ł��B�q�������́A�}���{�����e�B�A����̓ǂݕ������₨�b�̓��e������A�{�̐��E�ɓ����Ă���悤�ł����B��l���̖ʔ����s�������Ă����ʂł͏��A�S�z�����ȏ�ʂł́A����݂�Ƃ��Ă���p����A�P�N�����{����D���ȗl�q�������܂����B�}���{�����e�B�A�̊F�l�A�u���b��v���y�����Ȃ�悤��������i�߂Ă��������A���肪�Ƃ��������܂����B

�T���Q�R���i���j�P�E�Q�N�Ȃ��悵�W��
�����́A�P�N���ƂQ�N���́u�Ȃ��悵�W��v��̈�قōs���܂����B�P�N���ƂQ�N�����ꏏ�ɂȂ����O���[�v���V�ɕ����A���ꂼ��̃O���[�v�ŁA�Q�N�����l�����V�т��P�N���ƈꏏ�ɍs���܂����B�V�т̓��e�́A�u����܂��]�v�u�n���J�`���Ƃ��v�u�A�����J���h�b�W�{�[���v�u���e�Q�[���v�u�����߂����߁v�u�Ԃ�������߁v�ȂǁA���̓��Ɍ����āA�Q�N���̎q�������͂ǂ̂悤����P�N�����y���߂邩�A���ǂ��Ȃ�ɂ͂ǂ�������悢�����l���āA���̏W��ɗՂ�ł��܂����B�Q�N���́A�P�N���ɕ�����悤�ɒ��J�Ƀ��[����������Ă���l�q�������A�P�N�����f���ɘb���āA�ꏏ�Ɋy�������Ƃ����p�������܂����B�Q�N���̐U��Ԃ�ɂ��A�u�P�N���ɖ��O���o���Ă��炦���B�v�u�P�N���Ɋ��ł��炦���B�v�u�P�N���̂��Ƃ��l���Ċ����ł����B�v�Ƃ������z�����������܂����B�@�����傫���Ȃ����Q�N���̎p�ɁA�����������������������������Ƃ���ł��B�Q�N���A�����l�ł����B

�T���Q�Q���i�j�u�S�N�Q�g �����搶��������Ȃ����̉�v
�S��24���i�j���炨�x�݂��Ƃ��Ă��������搶���A�������畜�A���܂����B�S�N�Q�g�̎q�������́u�����搶�͍��A�E�����ɂ����ł����H�v�Ǝ��₷��q�����āA������\���\���Ɨ��������Ȃ��l�q�ł��܂����B�ł��A���������Ȃ��̂������搶�������ŁA�u�q�������ɑ���������̂ł����A�q���������������}������Ă���邩�S�z�ł��B�v�ƌ����Ă��܂����B���̐S�z�͂����ɐ�����сA�����搶�������ɓ������Ƃ��A�q�������̏Ί�ŁA�p�b�Ƌ��������邭�Ȃ����悤�Ɏv���܂��B�����Ɍ����Ďq�������͏��������Ă����悤�������搶��Ō}������A�i��̎������O�ɗ����A�u�����搶�A��������Ȃ����̉�v���n�܂�܂����B�i�s�����e���S�Ďq�����������������ōl�����悤�ŁA�݂�Ȃ��y���߂�V�тƂ��āu�卪�����v���n�܂�܂����B�����搶�ɑ������������Ă���q���ƂĂ��y�������ɓ����Ă���p����ۓI�ł����B�q�������Ɛ搶�̏Ί炪�P�����������āA���t�Ƃ����d���̖��͂����������ɂȂ�܂����B�����搶�́A���T����̒S�C���A�Ɍ����č��T�͖����������A���X�ɐg�̂����炵�Ă܂���܂��B
�S�N�Q�g�̊F����A�����搶�Ɗy�����w���������Ă����Ă��������ˁB
�T���Q�P���i���j�u�q�������W�҂���Ƃ̏�������v
�����̒��̎��Ԃ́A����芈���ɂ����͂����������Ă��鐅���n�掩����̍��X�؉�A������������V������A����������������A�w�Z�^�c���c��u����AAPOC����w�Z�^�c���c��̖��c����ƈꏏ�ɓo���Z�̌����ɂ��Ă̏���������s���܂����B�w�Z����́A�����{�����e�B�A����ւ̓����̊��ӂ̋C������`����ƂƂ��ɂP�E�Q�N�������̉��Z���̏ɂ��Ă��`�����܂����B�P�E�Q�N�������́A�w���ɓo�^���Ă��鎙�����N���X�̂R���̂Q���x���܂��B���̂��߁A���l���ł̉��Z�ǂɂȂ�₷�����ɂȂ��Ă���̂ł����A�����������{�����e�B�A����ł��B�P�E�Q�N���̉��Z��c�����Ă���ƂƂ��ɁA�n��ɂ���ẮA���Z�̑Ή��ɂ��ėj�����Ƃɕ��S�����Ă��������Ă��܂����B�܂��A�ی�҂̕������Z�̎��ɂ����������Ă���Ƃ������������Ă��������܂����B���̒n��̕��X�A�����āA��������A���ꂳ����̌����̂������ŁA�q�������̈��S������Ă��邱�Ƃ����߂Ď������܂����B�܂��A�����{�����e�B�A������q�����������킢���ƌ����Ȃ�����A�u�`�N�v�u�`�����v�u�`����v�̒��Ŏq���������ǂ̌Ă�����C�����悢����A���Z���ɍ����������ĉƂ܂ł̋A�肪�x���Ȃ鎙���ւ̐������̎d���ȂǁA�C����������������悤�ł��B
�u�q�������͒n��̕�v�ƌ����Ă������錩���{�����e�B�A����ł��B�q�������ɂ́A�ڂ����Ĉ��A������ƂƂ��ɁA���S��̃A�h�o�C�X�����ۂɂ́A�f���ɕ��������悤���Ƃł����b���Ă��������B
�����̌�ʎ��̂Ŏq����������Q�ɑ����Ă�������������܂��B���̌��ꏬ�w�Z���u���S�E���S�v�Ȋ��ł��葱����悤�A�F�l���������Ƃ����͂����肢�������܂��B

�T���Q�O���i�j�u���j���Ɓi�P.�Q�N���j�v
��T�̂P�T���i�j����{�s���j�ϑ����Ɓu�X�C�X�C�v���W�F�N�g�v�ɂ�鐅�j�w�����n�܂��Ă��܂��B�T���́A�P�E�Q�N���̎����i�ȉ��A�{������j���u���R�X�C�~���O�N���u�v�ɂĐ��j�̎w�����܂��B�{���Ƃ́A�w�K�w���v�̑̈�҂̓��e�܂��Ȃ���A���ꏬ�w�Z�S�����̉j�͌���Ɓu���̎��́v���疽�������@���w�Ԃ��Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B�{������́A�P�R�F�R�O�߂��Ɋw�Z���o�����܂����B���j�o�b�O��厖�����ɕ����Ă̏o���ł����B�Q��ڂƂ������Ƃ�����A�X�C�~���O�N���u������A�����̒��ւ����P��ڂ����X���[�Y�ɂł��Ă��܂����B�v�[���T�C�h�ɐ���E���A�A���܂�Ȃǂ̐���������A���悢��v�[���ւ̓����ł��B�����ƏΊ�Ŏ����v�[���̕��͋C����C�ɉ₩�ɂȂ�܂����B�w�����ɂ��w���ɂ��S�̂ł̐����ꓙ�́A����̗F�B�̓������������茩�āA�������s�����Ƃ��鍂���ӗ~���\��Ă��܂����B�ǂ̎������O�����Ɉꐶ�������g�߂Ă���A���ꂩ��̖{������̐��j�ɂ�����L�сE�������y���݂ɂȂ�܂����B������Q�Q���i�j�́A���R�X�C�~���O�N���u����̂������̂��ƁA�ً}���[���ł��ē�����Foams�ɐ\���݂����������ی�҂̕��̂ݎQ�ς��\�ɂȂ�܂����B���ߐ�������{���ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���s���������́A���q�l�̗l�q�����ЁA�������������B�Ȃ��A�R�E�S�N���A�T�E�U�N�����R��ڂ̐��j���Ƃ����{����ۂ́A���ē����������܂��̂ŁA���̍ۂ͂��Q�ς��������B

�T���P�U���i���j�@�Q�N���}��H��w�K
�Q�N���͐}��H��u���炳�� �ǂ�ǂ�v�Ƃ����w�K���s���܂����B����́A����̍��ɐ��������Ď�Ƒ��Ŋ��G�𖡂킢�Ȃ���A���`�����Ɏ��g�ނ��̂ł��B�q�������͌����@������A�ł߂��肷��Ȃǖ����ɂȂ��Ă���l�q�ł����B�g���l�������A���̒��ŗF�B�Ǝ肪�Ȃ����Ċ��ł���q���������A���킢�炵�������ł��B���ɂ́A�g�̂̂قƂ�ǂ����ɖ����点�ĐS�n�悳�����ɂ��Ă���q�����āA�܂�ŊC������ɂ��邩�̂悤�Ɋy����ł���q�����܂����B�Ȃ��Ȃ�����V�т�����@��������Ă��Ă���q�������ɂƂ��āA���������C�����ɂ��Ȃ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�@�������Ȏq�������̏Ί炪����ꂽ���ʁA�Q�N���̕ی�҂̊F�l�̐��𑝂₵�Ă��܂��\����Ȃ�������������ł����B

�T���P�U���i���j�@�U�N���������K�i�ƒ�ȁj
�U�N���̒������K�ł́A�g����u�߁h�ɒ��킵�܂����B�T�N���̎��ɂ��ȒP�Ȃ��̂������o��������̂ŁA��ۂ悭��Ƃ��Ă��܂����B����A�Ή����A�����߂鏇�����H�v���Ĕ����������Ȗ���u�߂��������܂����B�����̍��������u�߂����掩�^���Ă��鎙�������āA�u�������������I�v�Ǝ����C�Ȏq���������A���킢�������ł��B�������K��������́A�����������ς��ɂȂ��Ă��܂��A���H���c��₷���Ȃ肪���Ȃ̂ł����A�������U�N���ł��B�������A���H���A�قڊ��H�ł����B�U�N���̊F����A���Ƃ̐l�ɂ����Ѝ���Ă����Ă��������ˁB

�T���P�T���i�j�@�T�N���������K�i�ƒ�ȁj
�T�N���A�ƒ�ȁu�N�b�L���O�͂��߂̈���v�ł́A���M���钲�����@�̊w�K���s���Ă��܂��B���߂Ă̒������K�ł́A�u�����̓�����v�ł��B�g�������A�₩����g�������̂킩�����A�}�{�̎g�����ȂLj��̊w�K��F�B�Ƌ��͂��Ȃ���u�������������̓�����v���w�K���܂����B�݂�Ȃň��ނ����Ɋ��������l�q�̎q���������ƂĂ���ۓI�ł����B�ƒ�Ȃ̎��Ƃ��I����ۂɒS������،��搶����u���ЁA���Ƃł��������������̓�����ɒ��킵�Ă݂Ă��������B�v�Ƃ̂��b������܂����B���ЁA���ƒ�ł��q�l�ɂ���������@��������Ă���������Ǝv���܂��B�u�������K�v�Ƃ������t���q�������ɂ͖��͓I�ł������悤�ŁA�ƂĂ��ӗ~�I�Ɏ��g��ł��܂����B���͐��g���āu���Ђ����v�ɒ��킵�܂��B�n�����g�p���܂��̂ŁA����̂Ȃ��悤�݂�ȂŋC�����Ȃ�����g��ł����܂��傤�B

�T���P�S���i���j�u�n�b�s�[�t�F�X�e�B�o���i�S�Z�W��j�v
�����͎q���������ƂĂ��y���݂ɂ��Ă����u�n�b�s�[�t�F�X�e�B�o���i�S�Z�W��j�v������܂����B�S�Z�W��̖��O�́A���N�A�w����\�ψ���V�������O���W���A�u�n�b�s�[�t�F�X�e�B�o���v�ƌ��܂�܂����B�n�b�s�[�t�F�X�e�B�o���ł́u���ٓ��v���X�}�C���[�ǂŐH�ׁA�u�{�i����܁i�S�Z����܂��]�j�v��S�Z�����ōs���܂����B�S�Z�����Łu����܂��]�v�͐�������́H�Ǝv���Ƃ���ł����A�������w����\�ψ���ł��B������₷�����[����������Ă���܂����B���ꏬ�̎q�����������[�����悭���������Ă����悤�ŁA�i�s���鎙���́u����܂��]�v�̌Ăт����̍Ō�́u���v�̂Ƃ��́A�C�����������قǑS�����u�s�^�b�v�ƐÎ~���Ă��܂����B���̌�A�X�}�C���[�ǂ��ƂɁu�h�b�W�{�[���v�u�h���P�C�v�u�����S�v�u�����[�v�u����v�ȂǁA���������Ō��߂��V�т��s���܂����B�V�C�ɂ��b�܂�A���������Ȃ��瑖����A�����⋋�����Ȃ�����^���ԂȊ�����Ă���q�������̎p�����������A�u�y�����I�v�Ƃ������������������Ƃ��ł��܂����B�n�b�s�[�t�F�X�e�B�o���́A�w����\�ψ���U�N�������S�ƂȂ�A�݂�Ȃ̈��S���S���ӎ����Ċ������Ă���p��A�q��������l��l�����������łȂ��A�݂�Ȃ̂��Ƃ��C�ɂ��Ȃ��犈�����Ă���S�Z�����̎p�������A�݂�Ȃ�����ɂȂ����悤�Ɏv���܂��B�ی�҂̊F�l�A���q�l�̂��ٓ��̂������ɂ����͂��������܂��āA���肪�Ƃ��������܂����B�q�������̂��ٓ���H�ׂĂ��鎞�̏Ί�́A�{���ɑf�G�ł����B�����̊����̓��e�����q�l�ɁA���ЁA�����Ă݂Ă��������B

�T���P�R���i�j�u�Q�N�������ȕc�A���v
�����͐�̉��A�Q�N���̐����Ȃ̊w�K�ŕc�A�������܂����B���O�w���ŒS�C�̋{��搶����q�������ɕc�̐A�����̎w���ɉ����A�u�c�́A�N�����̘b���Ă����B�v�ƁA�A�����l�Ԃ⓮���Ɠ����悤�ɒ��J�Ɉ������Ƃ̑�����w�����܂����B�A�����c�́u���イ��v�Ɓu�Ȃ��v�Ɓu�s�[�}���v�ł��B�q�������̓|�b�g���͂����A�s�������Ȃ��悤�ɁA���J�Ɉ����Ă��܂����B�q�������͊w�K�̐��ʂ������Ɠy�̐[�����|�b�g�Ɠ����[���ɂ���悤�F�B�Ƙb�������Ȃ���c��y�ɐA���Ă��܂����B���Ɏq�������Ɋ��S�������Ƃ́A��̃|�b�g��y�̒��ɓ���Đ[�����m�F������ŐA���ւ��Ă������Ƃł��B����́A�q�������ɋ����Ă��Ȃ������̂ł����A���������ōl���ĕc��A����H�v������ꂽ�̂͑f���炵���Ǝv���܂����B�܂��A�u�c�́A�N�����̘b���Ă����B�v�Ƃ����{��搶�̌��t����������Ǝ~�߂Ă����q�������́A���������鎞�Ɂu������������ĂˁB�v�u�傫������ĂˁB�v�ƁA�C���������߂ē`���Ă���p�ɂ��ق�����Ƃ����C�����ɂȂ�܂����B���ꂩ��A�c�̐���������I�Ƀ^�u���b�g���ŎB�e���Ȃ���A���������͂��Ă����܂��B�_�앨�̐����ɂ����܂����A�H��ɂȂ���w�K�ɂ��Q�w���͂Ȃ����w�K���ł����炢���Ȃƍl���Ă��܂��B

�T���P�Q���i���j�@�R�N�������E�ݑ̌�
�����O��G�߂ɂȂ�܂����B�����͂R�N�����u�����I�Ȋw�K�̎��ԁv�œ���]�ɂ��钬�c����̒����ŁA���E�ݑ̌������܂����B�@�q�������͒��E�݂ɋ����ÁX�ŁA�u�搶�A��������E��I�v�ƁA�S�_���_�̏Ί�������Ă���܂����B�����݂�����o���̂Ȃ��q�������́A���������t�̏_�炩�����S�n�悢�悤�ŁA���̏ꂩ�痣�ꂽ����Ȃ��l�q�ł����B���̌�A���c����������������̟�����������Ă��炢�A�����������E���t���g���Ĉ��݂܂����B�}�{�œ���邨�������ނ̂����߂ĂƂ����q�����܂������A���t�������A�Y�̂��܂ǂ�����̂����߂ĂƂ����q���������܂����B���������݂Ȃ���A�Y�̂��܂ǂ̂ʂ�����������Ă���l�q���^�C���X���b�v�������E�̎q�������̂悤�Ɍ����A���܂��������ł��B�q����������́u�ォ��a�݂����Ă��������I�v�u�Ȃ�Ă���ƊÂ݂�������I�v�ƁA��l�т����Ƃ������Ă��鎙�������܂����B���c����ɂ́A�u�����v�Ɋւ��邱�Ƃ̊w�K�����łȂ��A�̂̂��炵��l�q�ɂ��Ă��A�����Ă��������܂����B�@���c������͂��߁A��������̑̌��w�K�̏����ɂ����͂����������{�����e�B�A����A����蓯�s�����Ă����������{�����e�B�A����A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�T���P�O���i�y�j
�u���R�H�ƍ��Z�o�X�P�b�g�I��Ƃ̌𗬉�v
�����́A���R�H�ƍ��Z�̃o�X�P�b�g�{�[�����̑I������������A�U�N���Ƃ̌𗬉���s���܂����B�U�N�����U���ɎR�����w�Z�Ƃ̃~�j�o�X�����s���܂��B���̃~�j�o�X���Ɍ����ĂU�N���̋@�^�����߁A���Z�����班���ł��Z�p�⒇�ԂƂ̊ւ�荇���p���z�����A���ꂩ��̊w�Z�����ɂ��������Ăق����Ƃ����肢����A���R�H�ƍ��Z�̃o�X�P�b�g�{�[�����̌ږ�̉����搶�ɂ��肢�����āA����̌𗬉�����ł��܂����B���Z���̑I��͗��Z����������C�����̂悢���A�����Ă�������A�U�N���ɑ��Ă��D�����Ί�Őڂ��Ă���܂����B�U�N���̖ڂ̑O�ōg�����������Ă��ꂽ���́A���ԓ��m�̑傫�Ȑ��̊|��������V���[�Y����u�L���b�L���b�I�v�ƕ������錃�������C�����̈�ْ��ɋ����n��A�U�N���͂��̔��͂Ɉ��|����Ă����悤�Ɏv���܂��B�Z�p��X�s�[�h���A�^���Ɏ����ɂ̂��ގp�ْ̋������ς��A��Ɋ�����f���炵�������������Ă��炢�܂����B���̌�A�I�肩��U�N���̓p�X��V���[�g�̗��K���@�����H�I�ɋ����Ă��炢�A�I������������Ď������s���܂����B�U�N���̎q�������́A�N��̐l�����Ƃ̌𗬂�����@��Ȃ��Ȃ��Ȃ��������߂��A�ŏ��͂ƂĂ��ْ����Ă���l�q�ł������A�𗬉�̏I�����鎞�ɂ́A��������̏Ί炪�����A�{���ɖ����C�ȗl�q�ł����B�U�N���̊F����A�����͖{���ɑf�G�Ȍo�����ł��܂����ˁB���R�H�ƍ��Z�̑I��̊F����Ɋ��ӂ̋C������Y��Ȃ��ł��������ˁB���R�H�ƍ��Z�̑I��̊F����A�ږ�̉����搶�A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�T���X���i���j�u�X�}�C���[�lj�c�v
�����̒��̎��Ԃ́A�X�}�C���[�lj�c���s���܂����B��c�̓��e�́A���T�T���P�S���i���j�ɍs���u�n�b�s�[�t�F�X�e�B�o���i�S�Z�W��j�v�ŁA�e�X�̔ǂŗV�ԓ��e�����߂邱�Ƃł����B�q����������́A�u�d�q�����W�S�v�u�X�S�v�u�����S�v�u�����S�v�u�h�b�W�{�[���v�u�h���P�C�v�ȂǁA�ǂ̃X�}�C���[�ǂ��U�N�������S�ƂȂ�A�݂�Ȃ̎v�����ɂ��Ȃ���V�т̓��e�����߂Ă���l�q�������܂����B���[���̕�����Ȃ��q������ƁA���ɐ}�ŕ\���A���t��I�тȂ�����������Ă���U�N���̎p����ۓI�ł����B�e�X�̔ǂ݂̂�ȂŌ��߂��V�т̓��e�ł��B�u�n�b�s�[�t�F�X�e�B�o���v�ł́A�݂�Ȃŋ��͂��A�݂�ȂŊy����Ŏv���o�Ɏc���ɂ��Ă����܂��傤�B�Ȃ��A�n�b�s�[�t�F�X�e�B�o���̓��́A���ٓ��̓��ł�����܂��B�X�}�C���[�ǂł��ٓ���H�ׂ邱�ƂɂȂ�܂��B���ٓ��̂����������肢�������܂��B

�T���W���i�j�u�Z���^�C���v
���T�ؗj���A�{�Z�̒��̎��Ԃ́A�Z���̊�b�w�͒蒅��ړI�Ƃ��āA�u�Z���X�L���v�̎��Ԃ�݂��Ă��܂��B���̎��Ԃ́A�w�K�x���{�����e�B�A���q�������̊w�K���e�̊ەt����������A�������̃q���g��^������A�ł��Ă���Ƃ����J�߂��肵�āA�q�����������M�������Ċw�K�Ɏ��g�߂�悤�w�߂Ă���Ă��܂��B�����́u�R�N���̂����Z�����}�X�^�[����v�Ƃ������Ƃ�ړI�ɁA��������̃{�����e�B�A����ɂ����͂��������A�S���ł����Z���̈Ï����s���A�C�����̂悢�傫�Ȑ��ŋ��������Ă��鎙������{�����e�B�A����̂Ƃ���ɍs���āA���̊e�i����Έ�ŕ����Ă��炤���������Ă��܂��B�{�����e�B�A����ɕ����Ă��炢�A�u�����Z���v��S���}�X�^�[���悤�ƁA�ꐶ�����Ɏ��g��ł���R�N���̎p�ɁA�ƂĂ����S�������܂����B���T�́A���̈Ï����I�����q����A���̕S�}�X�v�Z�ɒ��킵�܂��B�{�����e�B�A�̊F�l�A���T�����������A�����͂����肢�������܂��B

�T���V���i���j�@�N���u�E�ψ���Љ�
�{���A�̈�قɂĊw����\�ψ���̎i��ɂ��A��������u�N���u�E�ψ���Љ�v���s���܂����B���\�����\�����́A���ꂼ��̃N���u�E�ψ���̒��ł��B�X�e�[�W�ɗ����A��l�ЂƂ肪�l�����Љ�錾�t���͂�����ƑS�Z�����ɓ`�����܂����B��\�����́A�ǂ̂悤�ȓ_��`���������A�m���Ăق����|�C���g�Ȃǂ����A���\���邱�Ƃ��ł��Ă���A�����ւS�������܂����B���\���Ă��鎙���̑ԓx�������ւh�ł����B�b���l�̕������āA���\���鎙�����������Ă���悤�ɕ����A���\���I����x�ɁA�C�����̂����������肪�����Ă��܂����B�N���u��ψ���ɏ������Ă��鎙�����A���N�x�ȍ~�ɏ������鎙�����A�����Ɗ��҂ƍD��S�������Ē���̎��Ԃ��߂������Ƃ��ł������ƂƎv���܂��B

�T���Q���i���j�u�X�}�C���[�V�сv
�����̒��̎��Ԃ́A�Z��Łu�X�}�C���[�V�сv���s���܂����B�u�X�}�C���[�V�сv�́A�c����ǂ̎q���������A�݂�Ȃŋ��͂��Ĉꏏ�ɗV�Ԋ����ł��B�����̑�P��u�X�}�C���[�V�сv�͂U�N�����哱���A�ǂ̏c����ǂ��l�X�Ȗʔ����V�т̓��e�ł����B�Z��ł͂��ꂼ��u�h�b�W�{�[���v�u�h���P�C�v�u����܂��]�v�Ȃǂ̊������s���A�Ί�ɂȂ��Ă���q�������̎p����ۓI�ł����B�����̂P�T�����x�̗V�тł����Ă��A���̗V�тɌ����āA�U�E�T�N���͑��k�������A�������e�����߂Ă��܂����B����ꂽ���Ԃ̒��ŁA���k�E�������Ă���U�N���̎p�͖{���ɗ��h�ł����B�܂��A�ꏏ�ɂȂ��ď��グ����A��w�N�̎q�ǂ��ɗD�����T�|�[�g�����Ă����肵���T�N���̎p�������A�ւ炵���v���܂����B�U�E�T�N���A�����́A���肪�Ƃ��������܂����B���ꂩ�����������u�X�}�C���[�V�сv�͂���܂��̂ŁA���ЁA�݂�Ȃ����悭�A�Ί�ɂȂ�銈���ɂȂ�悤���ꂩ�����낵�����肢���܂��B

�T���P���i�j�u�݂���}���\���v
�{�Z�ł͗�N�A�w�Z����ڕW�̈�w�����܂����q�x�̈琬��ڎw���āA�ؗj���̋Ɗԋx�݂ɑS�Z�������u�݂���}���\���v�Ɏ��g��ł��܂��B���N�x����������u�݂���}���\���v���n�܂�܂����B��N�A�u�݂���}���\���v�́A�^���ψ������S�ƂȂ�A�����^�����s���Ă���Ă��܂��B���N�x�͐搶�Ɖ^���ψ��̎q���������ψ�������ŁA�܂��������ł��Ă��Ȃ������悤�ł��B�������A�������^���ψ��ł��B�ψ�������łȂ��Ă��A���������Ŋe�w���̒S�����x�ݎ��Ԃ��g���Č��߂Ă����悤�ŁA�{���̈ψ���������������łł��Ă��邱�ƂɁA���������E���͊��S���܂����B�����āA�ŏ��̂P���͉^���ψ����y�[�X���[�J�[�ƂȂ�A�N���X�ŏW�c�����s���A���̌�A�q�������������̃y�[�X�łR���ԑ���܂��B�q�������́A���C�悭�r��U��A�ꐶ���������Ă��܂����B�㔼�ɂȂ�A���Ă���Ƃ���ł����A�S���A�������ƂȂ��A�����̃y�[�X�ő����Ă���p�ɂ����S�������܂����B���ꂩ�珋���Ȃ��Ă��܂��B�����⋋�����܂߂ɂƂ�Ȃ���A�݂�Ȃň��S�E���S�Ȑ�����S�����Ȃ���A�����܂����̂������Ă����܂��傤�B

�T���P���i�j�@�u�P�N�����H�Q�ρv
�����́A�P�N���̕ی�҂̋��H�Q�ς�����܂����B���H�̏����̎��ԂɂȂ�ƁA�����̕ی�҂̕��̎p�������A�q�������͔z�V�����ی�҂̕��X���C�ɂȂ��Ă���l�q�ł������A���܂ł̗��K�̐��ʂ����A���������ċ��H�̏��������Ă��܂����B���H�̏����������A�ی�҂̕��X�������ɓ����Ă���ƁA�q�������̊�т̓s�[�N�ɒB���A�����ȏ�ɋ��H����������H�ׂ悤�Ƃ������͋C�������܂����B�u���������܂��B�v�������q�������́A�����������ɐH�ׂĂ��܂����B�P�N���́A�܂����H�W���ڂł��B���Ԓʂ�Ɂu�����������܁v�����邱�Ƃ́A�܂��܂�����i�K�Ȃ̂ł����A�����͕ی�҂̊F�l�̉����ɂ��A������葁���Еt���邱�Ƃ��ł��܂����B�݂�Ȃŋ��͂ł������Ƃɔ��肪�ł��āA�P�N���̎��M�ɂ��Ȃ������ƂƎv���܂��B�ی�҂̊F�l�A�{���͂��肪�Ƃ��������܂����B

�S���R�O���i�j�u�u�b�W��v�Ɓu�w�Z�^�c���c��v
�����̋Ɗԋx�݂́u�u�b�W��v������܂����B�Z���搶����́A�q�������̋C�����̗ǂ����A�⒩�}���\���Ɏ��g�ގp�A�^�ʖڂɊw�K�Ɏ��g�ޑԓx�ȂǂS���̎q�������̗l�q��U��Ԃ�A��������̔��i�فj�߂Ƃ���������A�q�������̊撣���F�߂Ă��܂����B���̌�A�����̐����ڕW�������搶�����b���܂����B�����̐����ڕW�́A�u���Ԃ���낤�v�ł��B�����搶���玞�Ԃ���邱�Ƃŗǂ��X�^�[�g�����ƂƂ��Ɏ��Ԃ��S����Ƃ肪���܂�A�W�����Ċw�K�ɗՂނ��Ƃ��ł���Ƃ������b������܂����B�܂��A���Ԃ���邱�Ƃ́A�w�͂����܂�₷���Ȃ邱�Ƃɉ����A�q�������łȂ��A��l�ł����Ԃ���邱�Ƃ́A�M�p�����l�ɂȂ��Ƃ������b�ł����B���Ԃ�����āA�������݂�Ȃ��C�����ǂ����������Ă����܂��傤�B�����̍u�b�W��́A�w�Z�^�c���c��̕��X���q�������̗l�q�����ɂ��Ă��������܂����B�w�Z�^�c���c��Ƃ́w�w�Z�̉^�c�ƕK�v�Ȏx���ɂ��āA�w�Z�ƕی�ҁA�n��̐l�Řb��������x�ł��B���R�ɂ��������ɏW��Ƌ��c��s���܂����̂ŁA�Q�ς��Ă��������܂����B�܂��A�{���͂o�s�`�̐��c������Ȃ��������A�{�Z�̊w�Z�̏��w�Z�^�c�ψ��̊F����ɒm���Ă��������܂����B
�w�Z�^�c�ψ��̊F�l�A�ǂ����A��낵�����肢�������܂��B


�S���Q�W���i���j�Z�����C�i�~���u�K��j
�����͎q�����������Z������A���R���h�� ���앪���̕��X�ɂ����͂��������A�~���u�K����s���܂����B�N���Ă͂Ȃ�Ȃ����̂ł͂���܂����A�����̂P�E�Q�N���̐��j�w�K���₻�̑��̊w�Z�������ɂ����āA�q���̐S�x��~�̏ɔ����A���E������ÂɕK�v�ȑΏ������邽�߁A���N�s���Ă��܂��B�S�x��~���̐S�x�h���@�̍s������AED�̈����������łȂ��A���͂̎q�������ւ̑Ή���Y�������ւ̔z�����ɂ��āA�z�肳���Ώ���������S�����b�������A��ρA�ْ����̂��錤�C��ł����B���h���ɒʕĂ���A�~�}�Ԃ��w�Z�ɓ�������܂ł͂W�����x������ƌ����Ă��܂��B�����́A�~�}�Ԃ��w�Z�ɓ������A�~���m�Ɉ����n���܂ł̂W�����x�AAED�ƐS�x�h���@���J��Ԃ��P�����s���܂����B���R�A��l�őS�Ă����Ȃ����Ƃ͍���ł��̂ŁA���E������サ�Ȃ���Ή����܂����B���߂āA���E�����m�̋��͂̑���������܂����B�q�������̈��S����ɁA���S���Ċw�K�Ɏ��g�߂�悤�S���E�����w�߂Ă܂���܂��B���Z�������A�{���C�̎w�������Ă������������앪���̊F�l�A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�S���Q�T���i���j�R�N�Љ�Ȍ��w�`���T���`
�{���͂R�N�����w�Z�̒��T�������܂����B�o���O�ɍ]���搶�Ǝq�������͒��T���̖ړI���m�F���܂����B�w���̒��T���͊w�Z�̎���̒n�}�����邱�Ƃ��ړI�ł��B�w�Z�̎���̒n�}������ɂ́A�P�������ł͌��w������܂���B���̂��߁A����͊w�Z�̖k���i������ʁj�A���T�͊w�Z�̓쑤�i�����E�������ʁj�̂Q���Ԃɕ����Ē��T�����s���܂��B�x��ʂ�ɂ͎Ԃ�l�̍s�����������A��������̂��X�����сA���킢���݂��Ă��܂����B�N���x�E�Z�L�`���[�E���āE�������ȂǁA�q�������̓L�����L�����Ƃ��X�̈ʒu���m�F���Ă��܂����B�s�������Ƃ̂��邨�X���y�������ɘb���Ă����q�����܂����B��ʂ肩�痠�̓��ɓ���ƁA���̗l�q���ς��A�т┨�A�ƁX���������сA�Â��ȗl�q�ł����B�q�������͏������������Œn��̗l�q���ς�邱�Ƃ��w�т܂����B���T�R�O���i���j�̒��T���ł́A�k���Ƃ͈Ⴄ���̗l�q�����Ă���邱�ƂƎv���܂��B

�S���Q�S���i�j�@�̈�W��u��{�̎p���Ȃǁv
�{���̋Ɗԋx�݂́A�Z��Łu�̈�W��v�����{���܂����B�S�w�N�Ƃ��{�N�x���߂Ă̑̈�W��ł������ɂ��ւ�炸�A�W���E�������ł��Ă��܂����B�K�x�ȋْ����̒��A�̈�ɂ�����u�C��t���v�u�x�߁v�u�̈����v�̎p����A�u�O�ւȂ炦�v�u���E�v�̗��K���s���܂����B���ꂼ��́g�^�h����������Ɨ������A�w�N�ɉ��������x���Ŏ��s����͂���ł����A������ӎ����u�悢�Ƃ����^�����悤�B�v�u�݂�Ȃƃ^�C�~���O�����낦�����B�v�ȂǁA�O�����Ȏp���������A���S�������܂����B�������A���̒��S�ɂ����̂�6�N����5�N���ł����B���ɁA6�N���͎�����̒��ڂ𗁂т����ł��A��������Ǝ�{����������A�f������ւ���ꂽ��A���̎p����ۂ��������肷�邱�Ƃ��ł��܂����B

�S���Q�S���i�j�u�Z���^�C���v
���T�ؗj���A�{�Z�̒��̎��Ԃ́A�Z���̊�b�w�͒蒅��ړI�Ƃ��āA�u�Z���X�L���v�̎��Ԃ�݂��Ă��܂��B���̎��Ԃ́A�w�K�x���{�����e�B�A���q�������̊w�K���e�̊ەt�������Ă���܂��B�w�K�x���{�����e�B�A����́A�q�������̎Z���v�����g�̊ەt�������邾���łȂ��A�������̃q���g��^������A�ł��Ă���Ƃ����J�߂��肵�āA�q�����������M�������Ċw�K�Ɏ��g�߂�悤�w�߂Ă���܂��B�{�����e�B�A�̊F�l�A���N�x���{�Z�̎q�������̂��߂ɂ��x�����������܂��悤�A�����͂����肢�������܂��B

�S���Q�R���i���j�@���y�W��
�����̋Ɗԋx�݂́A�u���y�W��v���s���܂����B���y��Ȃ̖،��搶����A�u�����A�����v�Ƃ������̖�������h�Ԃ̃T�C�������A���낢��Ȑ^�������钆�ŁA����O���ɍ��������o�����Ƃ��ӎ��������������K����n�܂�܂����B�����̗ǂ��̂��{�Z�̎q�������̓����ŁA�\�z�ǂ���A�q�������͖����≹���o�����K�Ɋy�������Ɏ��g��ł��܂����B���̌�A�{��搶�A�]���搶�A�����搶���A���ꂼ�ꉹ�̈قȂ�g�[���`���C�����o���A���̉��̍����ɍ��킹�āA��E���E���w�N�ɕ�����āA�n�[���j�[�̔������𖡂킢�܂����B�����āA�Ō�ɖ{�Z�̎q�������������̂���u�Z�́v���A�S���łP�Ԃ����̂��܂����B���Ԃ̓s����A�P�Ԃ����ɂȂ��Ă��܂��܂������A�܂��P�Q���Ԃ����o�Z���Ă��Ȃ��P�N�����u�Z�́v���̂���悤�ɂȂ��Ă��邱�ƂɊ������܂����B�ݍZ���̒�������u�����ƁA�̂������B�v�Ƃ��������o�Ă��āA�̂����Ƃ���D���ȂȂ��Ɣ��܂����C�����ɂȂ�܂����B�܂��܂��A�̂��݂�Ȃʼn̂��@��͂���܂��B�����ȉ̂��o���āA���ꂢ�ȉ̐����I���Ă��������B

�S���Q�Q���i�j�@�u �X�}�C���[�����| �v
�����͂P�N�������߂ĎQ�������u�����|�v�ł����B�����|�̒��O���U�N�����P�N���̋����ɏo�����A�����X�}�C���[�ǂ̐��|�ꏊ�Ɉꏏ�Ɍ������l�q�������܂����B�D���������������āA�U���Ă���U�N���̎p�������A����Ȃ�����A�P�N���̌��Ɏ�����Ă��肵�āA�ɂ��₩�ɐ��|�ꏊ�Ɍ������p����ۓI�ł����B���̌�A�Q�`�U�N�����P�N���̐��|�����̃T�|�[�g�����Ă���l�q���ǂ̃X�}�C���[�ǂł������܂����B�ق����̎g�����A�G�Ђ̎g�������A���J�ɋ����Ă���㋉���̎p�������A���̃X�}�C���[���|�̓`�������邩�炱���A��������������̋C�����������p����Ă���̂��Ɖ��߂Ċ����܂����B�l���̏��Ȃ����ꏬ�w�Z�ł����A�Z�ɂ̋������́A���̊w�Z�Ƃ��܂�ς��܂���B���ꂩ��̒����|�́A�P�N������͂Ƃ��Ċ��Ă��������܂��̂ŁA�݂�Ȃŋ��͂��āA���ꂢ�Ȋw�Z�������Ă����܂��傤�B

�S���Q�P���i���j�@�u�P�N�����H�J�n�v
�����́A�P�N�������߂ċ��H��H�ׂ���ł����B�P�N���͋��H�J�n�Ɍ����āA��T��2���Ԃɋ�̂��M���g���āA�^�ѕ��₨�M�̒u����������K���A�����̖{�Ԃɂ̂��݂܂����B�����́A���K�̐��ʂ�������Ɣ�������܂����B�z�V������q�����肵���������ŗ��Ƃ��Ȃ��悤�ɐT�d�ɉ^��ł���l�q�ł����B�܂��A���Ԃ̎q�������������̊��������߂Ăł������ɂ��ւ�炸�A�������ʂɋC�����āA���J�ɐ���t�������ł��Ă��܂����B�S���̔z�V���s���n������A�����������ȋ��H��ڂ̑O���V���搶���狍���̃X�g���[�̂�������H�ו��̒��J�Ȑ���������܂����B�����́w���X�g�����݂����N�x�ł��m�点�̂Ƃ���A���w���j�������ł����B���͓I�Ȍ����Ɏq�������́u�����H�ׂ����I�v�Ǝv���Ă������ƂƎ@���܂����A�b����������ƕ����Ă��܂����B�u���������܂��B�v�̈��A�̌�A�X�[�v�̒��g�ɒ��ڂ����q���u�����I�X�[�v�̒��ɕ���������I�v�ƌ����܂����B�����́u�`�a�b�X�[�v�v���o�Ă������ł��̂ŁA�X�[�v�̕������������茩�Ȃ���H�ׂ邱�Ƃ��y����ł���悤�ł����B�傫�Ȍ��Ńp����j����A�u���������I�v�Ɩ����C�ɘb���Ă����肷��q�������̎p���A�ƂĂ����킢�炵�������ł��B�܂��A�����̓X�v�[�������ŐH�ׂ邱�Ƃ��ł��錣���������̂ɂ�������炸�A�����g���ĐH�ׂ悤�Ƃ���q������A���������������܂����B�P�N���̊F����A����������݂�Ȃŋ��͂��āA�����������H��H�ׂ܂��傤�B

�S���P�W���i���j�u�P�N�����H���K�v
���T��21���i���j����A�P�N�������H���n�܂�܂��B����ƍ����͂P�N���̋��H���K���s���܂����B���Ԑ�w�Z���H�Z���^�[�����̐H�ʂ₨�M�������肵�āA�P�N���̎q�������͔z�V�̎d�����w�K���܂����B���������A�q�������͊���ɋ��H�Z�b�g��R�b�v�A���u���V���������܂����B���̌�A���H���Ԃ̎q�����������H���𒅗p���āA�H�ʓ��̉^�ѕ����t�������V���搶���狳���A����ȊO�̎q����������ɂȂ�A�z�V�̗��K���s���܂����B���ۂ̂��o�A���M�����~�ɂ̂��āA���̏d�����������Ă���q�������́A�ƂĂ��T�d�ɉ^��ł���A�u����Ȃ��悤�ɂ��Ȃ��ᥥ��B�v�ƋC�����Ă���C�������`����Ă��܂����B���̕������́A��M600�~���x���邨�M�̉��l��m���Ă��邩�̂悤�ł����B�P�N���̊F����A���T���狋�H���n�܂�܂��B��������H�ׂāA���N�ȑ̂�����Ă����܂��傤�B�P�N���̕ی�҂̊F�l�A�T���P���i�j�́A�u���H�Q�ρv������܂��B���H���邱�Ƃ͂ł��܂��A���q�l�̋��H�̗l�q�����ɁA���ЁA���Q�ς��������B

�S���P�V���i�j�ψ����
�{���A���N�x���߂Ă̈ψ�������s���܂����B�ψ�����́A�w�Z���������ǂ����邽�߂ɁA�T�E�U�N���i�S�N���w����\�ψ������j�̎q�������������I�E�����I�ɍs�������ł��B�{�Z�ł́A�u�w����\�v�u���N�v�u�^���v�u�����v�u�}���v�̈ψ������܂��B�P�N�Ԃ̏��߂̊����ł��̂ŁA�搶�����犈�����e���q�������͋����A�ψ����A���ψ����A���L�������߂āA�P�w���̌v��𗧂ĂĂ��܂����B�w�Z���������ǂ����邽�߂ɁA�����ɉ����ł���̂����l���Ă���T�E�U�N���̎p�����������������܂����B�����搶����A�w����\�ψ��̊F����Ɍ����āA�u�����ɂ���F����͋��R�����ɂ���̂ł͂Ȃ��A��ՓI�ȏo��������āA�F�������ɂ��܂��B�����ɂ���݂�Ȃ����炱���A���͂������Ă��ǂ��w�Z���n���ψ�����ɂ��Ă����܂��傤�B�v�Ƃ������b������܂����B���̏o����ɁA�w�Z�̈���Ƃ��āA������l��l�����ꂼ��̈ψ����S���Ă���Ƃ����C�����ɂȂ��悤���E���ꓯ�A�x�����Ă��������Ǝv���܂��B

�S���P�U���i���j�@�u���P���v
�����́A���N�x���߂Ắu���P���v���s���܂����B�����Ŏ��Ƃ����Ă���Ƃ��ɒn�k���N�������Ƃ�z�肵�A���̌�A�Ђ������������ƂōZ��ɔ�������P���ł����B�S�Ă̍s������߁A������߂��̐搶�̌������Ƃ����ƁB�����Ă��镨��|��Ă��镨���瓪����邽�߁A�h�Г��Ђ����Ԃ邱�ƂȂǁA�q�������͗����������s�����Ƃ�A���邱�Ƃ��ł��܂����B���S��C�̍����搶�����P���̐U��Ԃ�����钆�ŁA�n�k���N�������ɂ́u���i���Ȃ��j�E���i���Ȃ��j�E���i��ׂ�Ȃ��j�E���i�ǂ�Ȃ��j�E���i���Â��Ȃ��j�v�̃��[�����q�������Ɗm�F���܂����B
�Z���搶������A�n�k�͂��N���邩�N�ɂ�������Ȃ��Ƃ������Ƃɕ����čЊQ���́A�����̂悤�ɗ��������āA�s�����邱�ƁB�����āA���b����߁A�݂�Ȃ̎w�����ʂ�₷���悤�ɁA�Â��ɍs�����A�����ƗF�B�̐g����邱�Ƃ�S������|�̂��b������܂����B
�܂��A�q�������Ɂu�ЊQ���̔��ꏊ�̊m�F����p�Z�b�g�i���A���H���j�̔����͂��Ă��܂����H�v�ƌ�������ɁA�����̎q����������������Ă��܂����B��������Ă��Ȃ����q�l�̂��ƒ�ɂ�����܂��Ă��A���p�o�b�N�̕ۊǏꏊ�A����ꏊ���A�n�k�Ȃǂ̍ЊQ���N�����ۂ̃��[�����m�F���Ă���������Ǝv���܂��B�������̐���́A�����{��k�Ђɂ��d�C�E���������~�܂������Ƃ�̌����Ă��܂��B���̑̌���n�k�̍ۂ̊m�F�������ɂ��Ă����q�l�̔��B�i�K�ɉ����āA���`������������K���ł��B�����̖����݂�Ȃ̖�����ɂł�����ꏬ�ł��葱����悤�����͂��������B

�S���P�T���i�j�����|
�����̒��́A�P�N�����������X�}�C���[�ǂł̐��|�������s���܂����B��N�x�܂Ő��|�����́A���H��ɍs���̂��ʗ�ł������A�{�N�x����E���E���j������{�Ƃ��Ē��̎��ԂɎ��{���Ă����܂��B15���Ԃ̒Z�����|���Ԃł͂���܂����A���̈ړ����@��ق����̑|�����A�G�Ђ̐@������ς��č�N�x�Ɏ����I�ɂQ����{�������ƂŁA�U�N���̎����𒆐S�ɁA�q�������́A�~���ɒ����|�Ɏ��g�߂Ă��܂����B�P�N���̊F����́A���T22���i�j�̒����|����X�}�C���[�ǂŎQ�����܂��B�U�N���̂��Z����E���o������͂��߁A�Q�N������T�N���̊F������D���������Ă���܂�����A���ꂢ�Ȋw�Z���ꏏ�ɂ����Ă����܂��傤�B

�S���P�S���i���j�P�T���i�j�x�ݎ��Ԃ̗l�q
����̒��͉J���~���Ă��܂����B�J�Ԃ��������₵�����ȗl�q�̍Z��ł������A�P�N�������̉�ŁA�V���搶����u�ɂ��v�̉̂̏Љ����A�u�̂���l�͉̂��Ă݂Ă��������B�v�Ƃ������b����A�P�N���̉��l���̎q�����������̉̂�m���Ă���悤�ŁA���C�ɉ̂��Ă���܂����B����ƁA����Ɠ܂��ɕς��A�Ɗԋx�݂ɂ͉J���~�݂܂����B���̎��Ԃ͍Z��ŗV�Ԃ��Ƃ��ł��Ȃ������̂ł����A�����x�݂ɂȂ�ƍZ��ŗV�Ԃ��Ƃ��ł��A�q���������搶���Z��𑖂����āA�y�������ɉ߂����Ă��܂����B�����̋Ɗԋx�݁A�����x�݂Ƃ��ɐ��ꐰ��Ƃ�����̉��A���̉Ԃт炪�������ŁA�q�������͌��C�ɍZ��ŗV��ł��܂����B�����́A�P�N�����U�N���̂��U�����āA�Z��ňꏏ�ɗV��ł��܂����B�P�N���ɂƂ��č����̋Ɗԋx�݂͏��߂Ă̊O�V�тł����B���Z����A���o����ƈꏏ�ɗV��ł���P�N���̏Ί炪�A�ƂĂ��P���Ă��܂����B

�S���P�P���i���j�@�u�P�N�����}�����v
�{���A�u�P�N�����}�����v��̈�قōs���܂����B6�N���Ǝ���Ȃ��œ��ꂵ�A�w�N���ƂɍH�v���ꂽ�w�N�Љ�A�S���ł́u�W���M�X�J���v�_���X�Ȃǂ����ĂP�N���̓��w���݂�Ȃŏj���܂����B��\�ψ��̂T�E�U�N��������{�ɁA�W���M�X�J���̃_���X�������ɏK�����Ă��܂����B�o�����_���X���j�R�j�R�ƌ��C�ɗx��A�����Ƃ����Ɨx�肽�����ł����B����̎��ɂْ͋����Ă���1�N���̕\����A���ޏꎞ�ɂ͏Ί�ƈӗ~�����킳�����\��ɕς���Ă����悤�Ɋ����܂����B���̌�́A�u�X�}�C���[�ǁv�獇�킹�ł��A�e�O���[�v�����ꂼ���̊��̂��镵�͋C�ŁA�悢�c���芈���̊���o�����ł��܂����B

�S���P�O���i�j�@���H�J�n